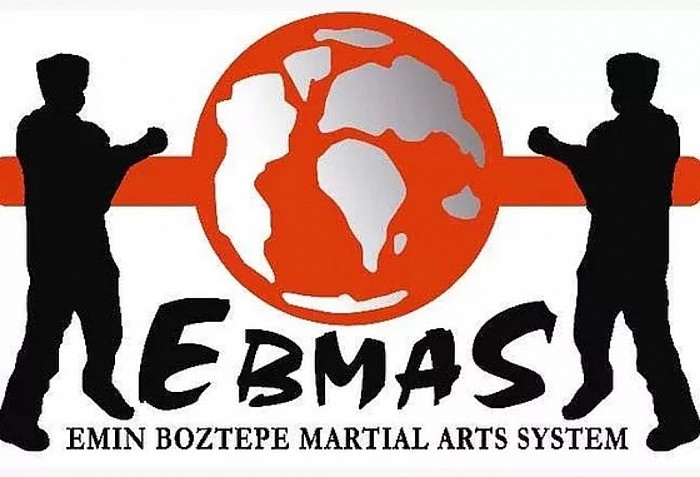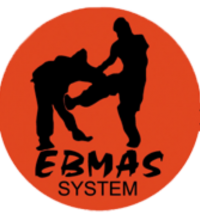詠春拳教室エブマス名古屋は、すべてのレベルの人々を歓迎し、伝統的な中国拳法を通じて自己防衛、身体の強化、ストレス解消などのメリットを提供します。
【最新情報】
2024年2月より名古屋市内で詠春拳ビジネスマン·クラスが始まります。
男女更衣室·シャワー室あり、仕事帰りに武術を学びたい方に、最適です。
【日時】毎週(金)19:00~21:00
【場所】名古屋市演劇練習館 アクテノン https://g.co/kgs/rd1fKNK
【指導】宮田光明 エブマス名古屋アシスタント·インストラクター
【問い合わせ】ebmasnagoya2024@gmail.com
【詠春拳の特徴】
詠春拳は、相手と接触した状態での練習が特徴となっています。
この方法によって、物理的な接触を通じて相手の動きや意図、エネルギーを「感じ取る」能力を養うことができます。
詠春拳の実践者は、相手の力や方向、圧力の変化を無意識に特定し、それに対応することができるようになります。
特に、相手の力の方向を変える技を習得するためには、詠春拳の練習法であるチーサオが非常に重要です。
反射神経は、実践者が攻撃に素早く反応し、反撃のチャンスを見逃さないために不可欠です。これは効果的な護身術を実践する上でも重要な要素となります。
詠春拳の練習生は、接触感度と反射神経を発達させるための練習を繰り返し行い、無意識のうちに詠春拳の技を使いこなす運動能力を目指します。
このようなトレーニングによって、詠春拳の特徴的な能力を高めることができるのです。
【練習内容】
※詠春拳の基本練習(型·チェーンパンチやパクサオ等技の反復練習)
※詠春拳の原理及び理論の説明、詠春拳の身体操作(技、ターン、フットワーク)
※対人練習(各シリーズ、チーサオ等)
※ラットサオ(感度トレーニング)、 対他の格闘技術(ボクシング的パンチ、キック、タックル、寝技等)に対する対応技法
※詠春拳技術の護身応用 (戦術と戦略)
※スピードup/スタミナup/パワー強化等
先ずは、基本の立ち方、構え、基本技とその理論について説明します。
小念頭という一つめの型には、詠春拳の九割程の技が組み込まれています。
パンチの練習では緊張しないようにリラックスしてパンチが打てるよう練習します。
詠春拳のパンチは、チェーン·パンチと言ってパンチの間が途切れることなく打ち出される、特徴的なパンチです。
次に、攻撃の強さに応じて相手の力を利用できるようにするために、対人での練習に移ります。
この練習が詠春拳の習得に非常に重要で多くの時間をこの練習に費やします。
【詠春拳メソッドと小念頭】
【詠春拳メソッドと小念頭】
詠春拳の練習生が始めに習う型が、シウ・ニム・タウ(小念頭)です。
シウ・ニム・タウ・フォームの特徴の 1 つは、練習生が練習中に一歩も動かないことです。
したがって、このエクササイズを実行すると、同時に下半身もトレーニングすることができます。
これが、詠春拳の練習生が、他のグンフー スタイルの練習生のようにスタンスを習得するトレーニングに時間を費やすことなく、すぐにシウ・ニム・タウ・フォームの練習を開始できる理由の 1 つです。
詠春拳の技は、相手の力を借りて、巧みに反撃できることを、目的としています。
カリキュラムの過程で、 1 つずつを、クリアしていく必要があります。
先ずは、自らの攻撃を優先せず、相手の攻撃力を逸らす練習に進みます。
相手の攻撃をそらすこと(deflection)に慣れたら、次は、相手の力を借りることを学び、向かってくる力を利用して攻撃できる身体操作を作ります。
相手の力を「借りる」ことができるようになると、相手の力を利用して反撃を行うため、全身のリラックスと軽やかな動作が重要です。
シウ・ニム・タウ・フォームは、一貫した努力とトレーニングによって望ましい結果が得られます。エブマス詠春拳では、曖昧さや混乱のない明瞭な動きが求められます。
シウ・ニム・タウ・フォームの実践は、常に注意を払って行う必要があります。各動作の位置に集中し、視覚は手に従い、自然でスムーズな呼吸を心がけましょう。緊張と不注意は避け、正確な動作を行います。
これらのポイントを守りながら練習を続けることが、詠春拳を習得するための近道となります。
継続した練習によって、相手の攻撃に対して自信を持ち、効果的な身体操作を行えるようになるでしょう。